こんにちは!クラールです!@klar_net1
今回は、高配当株についてお話ししていきます。
具体的に新NISAとの噛みあいはどうなのか?
高配当株は新NISAではどうしたらいいのか?
高配当株のスクリーニングはどうやればいいのか?など、なるべく具体的に色んな問題に対して最適解が見るかる様に記事を書いていこうと思います。
\ この記事を詠むことで /
高配当の特徴がわかる
高配当のリスクがわかる
新NISAと組み合わせる時の注意点(高配当株)
スクリーニングが何かわかる
高配当銘柄のスクリーニングのコツがわかる
高配当株は、投資家に配当金の形で収益を提供し、これにより安定したキャッシュフローを享受することができます。しかし、高配当株にはリスクも伴います。
企業の経済的健全性や市場の変動に影響を受ける可能性があるため、適切な投資戦略と注意深い分析が必要です。
この記事を通じて、高配当株に投資する際の重要な要素やアプローチを理解し、賢明な投資判断をする手助けとなる様に分かりやすく解説していこうと思います。
高配当株の特徴
配当金が多い

当然ですが、大前提となるのが配当金が多いことです。つまり利回りが3%以上又は、4%を超えているものを選定していきます。
配当金は、株式投資で得られる収益のひとつで、投資元本を回収したり、生活費に充てたりと、さまざまな用途に活用できます。
安定した収益

高配当株は、配当を安定して支払っている企業が多い傾向にあります。
理由として、成熟して安定した業績を継続してあげている大きな企業が多いからです。
配当を安定して支払うためには、安定した収益と財務状況が求められます。そのため、高配当株は、安定した収益を期待できる投資対象として人気があります。
リスクヘッジになる

業績が安定した企業が多い分、業種やセクターを分けて分散しているだけでリスクヘッジにつながります。
- 業績が安定している
- 財務状況が良好である
- 配当性向が高い
これらの特徴を持つ企業は、景気変動や市場の下落の影響を受けにくいため、株価の変動リスクが低いと考えられます。
また、配当性向が高い企業は、利益の多くを配当金として株主に還元しているため、配当金の安定性が高い傾向にあります。
購入するタイミングを考えなくていい
高配当株の大前提は成長より安定性にです。
つまり、キャピタル(元手)の上昇よりもインカム(配当)を重視した考えになります。
成長を促すグロース銘柄より、安定性を重視したバリュー銘柄に似た側面があるのも高配当株の特徴です。
つまり、チャートでいうと株価の値上がりでトレンド相場を狙うものよりは、一定の場所でレンジを組み続けている
レンジ相場の銘柄を狙うことを指します。
つまりインカム狙い
インカムを狙った長期投資ならば、銘柄を購入するタイミングを考えすぎる必要はありません。
高配当のリスク
価格変動リスクが大きい

高配当株は、配当利回りが高いため、価格変動リスクが大きい傾向にあります。
配当利回りが高いということは、株価に対して配当金の割合が高いということです。
そのため、株価が下落すると、配当利回りがさらに高くなるため、さらに売り圧力が強まります。
前述の通り、安定した業績を続けている企業が多いのが高配当株の特徴でもありますが、世界情勢やインフレなど
株価に与えるリスクは常にありますので、定期的な見直しは必ず行っていきましょう。
減配リスク

配当金は企業の業績によって定められているため、業績が悪化した場合、配当金の減配や無配の可能性があります。
特に、景気変動や市場の下落の影響を受けやすい企業は、減配リスクが高くなります。
キャピタルゲインが狙いにくい

高配当株は、配当金の支払いを重視するため、株価の上昇を目的とした投資には向いていません。
そのため、キャピタルゲインを狙う投資家にとっては、魅力的な投資対象とはならない可能性があります。
キャピタルゲインを狙っていくならグロース株など今後の成長が期待される企業に注目していきましょう。
配当金には税金がかかる

| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 企業の利益に対する課税 | 企業は、利益を得たときに法人税を支払います。そのため、配当金も、法人税が課された後に株主に分配されるものと考えられます。 |
| 資産の増加に対する課税 | 株主は、配当金を受け取ることで、資産を増やすことができます。そのため、配当金に対しても、所得税や住民税が課税されることになります。 |
配当金に税金がかかる理由
このように、配当金には、企業の利益に対する課税と、資産の増加に対する課税という2つの理由から税金がかかります。
配当金の税金の概要
| 税金 | 種類 | 税率 |
|---|---|---|
| 源泉徴収 | 所得税・住民税 | 所得税15.315%、住民税5% |
| 配当控除 | 所得税 | 所得金額や配当金の額によって異なる |
配当金の税金は、源泉徴収という制度によって、先に差し引いて支払うことになります。そのため、確定申告をしない限り、この源泉徴収された税金が最終的な納税額となります。
なお、配当金には、配当控除という制度もあります。
配当控除
配当控除とは、配当金に対して支払った税金を、一定の金額まで所得税から控除できる制度です。配当控除額は、所得金額や配当金の額によって異なります。
| 所得金額 | 配当控除額 |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 配当金の額 × 10% |
| 1,000万円以上 | 配当金の額 × 5% |
所得金額が1,000万円未満の人で、配当金の額が年間100万円の場合
所得1000万未満 配当所得金額(100万円)×10%=10万円
配当控除額は10万円となります。
配当金の税金は、複雑な制度ではありますが、基本的な考え方は、企業の利益を株主に分配する際に、税金を課すという点です。
新NISAの詳細
新NISAは、2024年1月から始まる新しいNISA制度です。現行のNISA制度(つみたてNISA・一般NISA)を統合し、より利用しやすい制度として改正されました。
新NISAの概要は、以下のとおりです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 対象者 | 18歳以上の国内居住者 |
| 口座開設 | 金融機関や証券会社で口座開設 |
| 投資対象 | 上場株式投資信託(ETF)と上場投資信託(投資信託) |
| 年間投資上限額 | 成長投資枠:240万円、つみたて投資枠:120万円(合計360万円) |
| 非課税期間 | 無期限 |
| 非課税投資枠の再利用 | 保有資産を売却した分だけ、再利用可能 |
| 口座開設期間 | 恒久化 |
新NISAは、以下の2つの枠から構成されています。
成長性の高い株式投資信託や投資信託を投資対象とする枠。他にも個別株やアクティブファンドなども対象。つみたて投資枠よりも対象銘柄が多い。
積立投資に適した株式投資信託や投資信託を投資対象とする枠
新NISAの変更点は、以下のとおりです。
- 年間投資上限額が拡大(従来の一般NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)
- 非課税期間が拡大(無期限)
- 非課税投資枠の再利用が可能になった
- 口座開設期間が恒久化された
新NISAは、投資のハードルを下げ、より多くの人に資産運用の機会を提供することを目的とした制度です。
※新NISAと現行のNISA制度との比較表
| 項目 | 新NISA | 現行のNISA |
|---|---|---|
| 対象者 | 18歳以上の国内居住者 | 18歳以上の国内居住者 |
| 口座開設 | 金融機関や証券会社で口座開設 | 金融機関や証券会社で口座開設 |
| 投資対象 | 上場株式投資信託(ETF)と上場投資信託(投資信託) | 上場株式投資信託(ETF)と上場投資信託(投資信託) |
| 年間投資上限額 | 成長投資枠:240万円、つみたて投資枠:120万円(合計360万円) | 一般NISA:年間120万円、つみたてNISA:年間40万円 |
| 非課税期間 | 無期限 | 一般NISA:5年間、つみたてNISA:20年間 |
| 非課税投資枠の再利用 | 可能 | 不可 |
| 口座開設期間 | 恒久化 | 一般NISA:2023年末まで、つみたてNISA:2042年まで |
新NISAは、投資のハードルを下げ、より多くの人に資産運用の機会を提供することを目的とした制度です。今後、新NISAを活用した資産運用がより身近なものになっていくと期待されます。
つみたて投資枠と成長投資枠の違い
成長投資枠
成長投資枠=240万円が最大/年間
- 上場株式
- 投資信託
- ETF(上場投資信託)
- REIT(不動産投資信託)
高配当株を新NISAで投資したい場合は、成長投資枠を利用する必要があります。
つみたて投資枠
つみたて投資枠=120万円が最大/年間
- 国内株式型インデックスファンド
- 外国株式型インデックスファンド
- バランス型ファンド
新NISAで高配当株投資をする時の注意点
複利効果を最大限活かせない
新NISAでは、配当金を再投資する場合、分配金で新たに投資することになるので、その年のNISA口座の非課税投資枠を使用することになります。
株式=配当金→再投資(課税対象)
投資信託(分配型)=分配金→再投資(課税対象)
投資信託(再投資型)=分配金→再投資(非課税)
例えば、ある年にNISA口座で100万円分の投資信託を購入し、2万円の分配金をもらえたとします。分配金の2万円は再投資されるので、その年のNISA口座の非課税投資枠を102万円(100万円+2万円)使用したことになります。
つまり、分配金を受け取った後に再投資に回すと課税対象となってしまうので、複利効果を最大化させる事が難しいという側面が出てきます。
 クラール
クラールボクの場合は、配当を生活費の足しにする様にしているので、日本株にも投資をしています。
ボクの場合
複利効果を最大限活かせないでお話しましたが、配当金が自分の手元に戻ったとき、そのお金で再投資をした場合には課税されてしまいます。



ボクは、どうせ課税されるのなら生活費の足しにした方がいいのでは?
という結論に至りました。
実際に、↓の記事にも書きましたが、子どもの学費、老後の生活費にも以下の金額が必要になってきます。
今のうちから貯蓄をしていったとしても、補える余裕はほしいですよね。
そんな時のために、高配当株の恩恵を使いたいところです。
| 学校種別 | 平均学費 |
|---|---|
| 小学校 | 公立約32.2万円、私立約159万円 |
| 中学校 | 公立約48.8万円、私立約140万円 |
| 高校 | 公立約45.7万円、私立約97万円 |
| 大学 | 国公立約240万円~260万円、私立(文系)約390万円、私立(理系)約540万円 |
| 夫婦2人の老後の生活費 | |
|---|---|
| 最低限の生活費 | 22万円/月 |
| 平均的な生活費 | 27万円/月 |
| ゆとりのある生活費 | 36万円/月 |


米国高配当株ETFでは30%課税が発生する
米国ETFの配当金に対する税金は、米国で約10%が差し引かれ、その後日本で約20%が差し引かれます。
米国10%+日本20%=30%の税金がかかることになる
配当控除で、10%~5%ほど安くすることがが出来ますが
どれだけ配当個所を使って減税をしたとしても15%~20%分の税金を支払う必要があります。
その点、日本株だと5%~10%に抑えることが出来るので節税効果を最大化させたい場合は日本株をメインに考えるといいかもしれません。
高配当銘柄は成長投資枠
成長投資枠=240万円が最大/年間
- 上場株式
- 投資信託
- ETF(上場投資信託)
- REIT(不動産投資信託)
高配当株を新NISAで投資したい場合は、成長投資枠を利用する必要があります。
現行NISAと新NISAは口座が違う
2024年から始まる新NISAは、現行のNISAとは別の口座になります。現在すでにNISA口座を開設している場合は、自動的に同じ金融機関の新NISA口座が開設され、すでに積立設定などされているものはそのまま引き継がれます。
NISA口座を開設している場合は、自動的に同じ金融機関の新NISA口座が開設される
すでに積立設定などされているものはそのまま引き継がれる
ただし、現行NISAでは取り扱いのあった投資信託などでも、新NISAでは取り扱いの無いケースもあるため注意が必要です。
新NISAでは取り扱いの無いケースもある
新NISAでは非課税期間の無期限化や、非課税保有限度額の拡大などの制度改正が行われます。新NISAの非課税保有限度額は1,800万円となり、より多くの金額を非課税で投資できるようになります。
ただし、1,800万円のうち成長投資枠で利用できるのは1,200万円までです。
高配当株の優良企業の特徴
安定したビジネスモデル
配当利回りが高い企業は、利益を安定的に出し続け、その一部を株主に還元する能力がないと成し遂げられません。安定した利益がある優良企業は定期的で安定した利益を出す強固なビジネスモデルを持っています。これは、一貫して長期にわたって高い配当を支払うための基盤となります。
- 利益が安定している
- 負債が少ない
- 減配していない
- 利益剰余金が上がっている
強固な財務体質
長期にわたって高い配当利回りを維持するには、優れた財務体質が必要です。低い負債比率や適切な流動性は、企業が経済の波乱でも安定した業績を維持する能力を示しています。
- 流動性比率が高い
- 自己資本比率が高い
配当への考慮
配当への考慮が高い企業の特徴として、減配していない事はもちろん、連続増配が行われている企業が多いのも特徴のひとつです。つまり、配当に対して積極的な企業が多い
- 配当性向がバランスが取れている
- 連続増配
- 減配していない
割安なものにも気を配る
高配当株に投資する際には、配当利回りだけでなく、割安度も考慮することが重要です。割安度とは、株価が企業の価値に対して適正かどうかを示す指標です。割安な銘柄は、投資リターンが高くなる可能性があります。
- PBRが低い
- PERが低い
ファンダメンタルズによる期待値で決める
ファンダメンタルズとは、国や企業などの経済状態などを表す指標のことで、「経済の基礎的条件」と訳されます。
国や地域の場合、経済成長率、物価上昇率、財政収支などがこれに当たり、企業の場合は、売上高や利益といった業績や資産、負債などの財務状況が挙げられます。
ファンダメンタルズをもとに株価や為替の値動きを予測することをファンダメンタルズ分析といいます。
ファンダメンタルズ分析では、ファンダメンタルズが将来の株価や為替の値動きに影響を与えると仮定して、ファンダメンタルズの変化を分析し、その変化が株価や為替にどのような影響を与えるかを予測します。
例えば、経済成長率が上昇すると、企業の業績が改善し、株価が上昇すると考えられます。また、物価上昇率が上昇すると、為替は円安に傾くと考えられ、輸出企業の業績が改善し、株価が上昇すると考えられます。
ファンダメンタルズ分析は、長期的な投資において有効な手法として知られています。しかし、ファンダメンタルズは短期的な値動きには必ずしも反映されるとは限らないため、注意が必要です。
具体的にファンダメンタルズによる影響が高まる事象
- 企業の財務諸表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書など)が良好で、収益性や成長性が見込まれる場合。
- 企業のビジネスモデルが優れており、競争力がある場合。
- 業界全体の環境やトレンドが良好で、その企業の業界での立ち位置が強い場合。
- 新製品の販売が好調で、大幅な業績拡大が期待できる場合。
高配当株の投資戦略
高配当株の選び方
- 配当利回り
もちろん、配当利回りは重要なポイントです。ただし、配当利回りだけを重視して選ぶと、価格変動リスクが高い株を選んでしまう可能性があります。
- 配当の安定性
配当の安定性は、高配当株を選ぶ際に重要なポイントです。配当を安定して支払っている企業は、安定した収益と財務状況を有していると考えられます。
- 業績の成長性
業績の成長性も、高配当株を選ぶ際に重要なポイントです。業績が成長すれば、配当金も増加する可能性があります。
高配当株の注意点
高配当株は、配当金が多いというメリットがある一方で、価格変動リスクが大きいというデメリットがあります。そのため、高配当株に投資する際には、以下の点に注意しましょう。
- 価格変動リスクを理解する
高配当株は、価格変動リスクが大きいため、投資する際には、価格変動リスクを理解しておきましょう。
- 長期保有する
高配当株は、価格変動リスクが高いため、短期的な投資には向いていません。長期保有することで、価格変動リスクを抑えることができます。
高配当株の例
2023年10月17日時点の、日本の高配当株の一例を以下に示します。
| 銘柄 | 配当利回り(%) |
|---|---|
| りそなホールディングス | 4.49 |
| 三菱商事 | 4.46 |
| 三井不動産 | 4.32 |
| 伊藤忠商事 | 4.21 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.99 |
drive_spreadsheetGoogle スプレッドシートにエクスポート
この表はあくまでも一例であり、実際の投資判断はご自身の責任において行ってください。
スクリーニングとは
スクリーニングとは、特定の条件に合致する対象を選別するプロセスです。
投資においては、投資対象となる株式や投資信託を、配当利回りや株価収益率などの指標に基づいて選別することを指します。
つまり
効率的に投資対象を絞り込むこと
をスクリーニングといいます。
具体的なやり方としては
- スクリーニングの目的を明確にする
スクリーニングを行う目的を明確にすることで、適切なスクリーニング条件を設定することができます。
人によってリスク許容度も違えば、投資額や投資年数も違いが出て来るのと同じで、スクリーニング方法もこれが正解!というものはありません。ですが一般的な目安はどの程度なのか数値を具体的に出していこうと思います。
- スクリーニング条件を慎重に設定する
スクリーニング条件を過度に厳しく設定すると、投資対象が絞り込み過ぎてしまい、投資の機会を逃す可能性があります。逆に、スクリーニング条件を緩く設定すると、投資対象が広がり過ぎてしまい、投資の判断が難しくなる可能性があります。
- スクリーニング結果を検証する
スクリーニング結果を検証することで、スクリーニング条件の有効性を判断することができます。
スクリーニングは、投資の効率化やリスク管理に役立つ有効なツールです。しかし、スクリーニングの結果だけで投資判断を行うことは危険です。スクリーニング結果を参考にしながら、投資対象を慎重に選定するようにしましょう。
高配当株のスクリーニング方法
高配当株の選定方法
人それぞれに、リスク許容度は違うのと一緒で、スクリーニング方法も人によって多種多様です。
なので、目安となる選定方法を下に並べてみます。
いくつか数値を設定して、自分なりのスクリーニングを考えてみてください。



数値を設定していますが、それが正解!とは思わず特性を理解して自分なりにスクリーニングしてね
おススメツール


配当利回り3〜4%以上
配当利回りとは1株当たりの年間配当金÷現在の株価で求められ、割合が高いほど、1株当たりに受け取れる配当金額は高いです。


高配当株の定義は明確に決まっていませんが、一般的には、配当利回りが3〜4%を超えている株が高配当株と認識される傾向にあります。


配当性向が30〜50
高配当株のスクリーニング条件において、配当性向が30~50%である理由は、企業が将来の事業拡大や投資に必要な資金を確保するために、一定の利益を留保することが必要だからです。
設備投資や新事業の展開など、更なる安定性、成長性を確保するには純利益で補う必要があるからです。
一方で、配当性向が高すぎると、安定性、成長性を促すことが出来ないので株価や配当金に影響が出てくるおそれがあります。
同じく、配当性向が低すぎると、株主に対する利益還元が不十分となり、配当による恩恵が少なくなります


その中で、30~50のバランスは、どちらにもバランスが取れている数値といえるので企業にも株主にも安心が出来きる数値とされていますが、業種などで設備投資などを必要とする、製造業やインフラを整備する事業などは比較的配当性向が低い業種もあることを認識しましょう。
計算方法はこちらの通り


| 配当性向 | 理由 |
|---|---|
| 0%未満 | 配当金を支払わない |
| 0%~30% | 内部留保を増やすため |
| 30%~50% | 適切な利益還元と内部留保のバランス |
| 50%以上 | 過剰な利益還元 |



配当性向=純利益の分配先の割合は30~50がバランスが取れている


目安として業種別の平均値(過去データを引用)
| 業種 | 配当性向(平均値) |
|---|---|
| 金融業 | 52.5% |
| 建設業 | 30.6% |
| 製造業 | 30.2% |
| 情報・通信業 | 28.9% |
| サービス業 | 27.9% |
ROE(自己資本利益率)の高さ3~5%以上
ROEとは
1株当たりの当期純利益を自己資本で割ったもので、企業の収益力を測る指標です。




ROEが高い企業は、自己資本を効率的に活用して利益を上げていると言えます。
- ROEが高い企業は、自己資本を効率的に活用して利益を上げている
- ROEが高い企業は、配当金を支払えるだけの利益を上げている可能性がある
- ROEが高い企業は、将来の成長可能性が高い可能性がある
なぜなら、ROEが高い企業は、自己資本を効率的に活用して利益を上げているため、将来の成長に必要な資金を調達しやすいからです。



ROEも業種によって集約率がことなるので、そちらも考慮にいれて指標を調べることが大切!
目安として業種別のROEの平均値(過去データを引用)
| 業種 | ROEの平均値 |
|---|---|
| 銀行 | 10%以上 |
| 保険 | 10%以上 |
| 不動産 | 5%以上 |
| 製造業 | 5%以上 |
| 小売業 | 3%以上 |
| サービス業 | 3%以上 |
| 業種 | ROEの平均値 |
|---|---|
| 情報通信業 | 10.2% |
| 電気機器 | 7.0% |
| 化学 | 4.5% |
| 鉄鋼 | 3.3% |
| 精密機器 | 5.6% |
| 食料品 | 8.6% |
| 医薬品 | 9.0% |
| 繊維製品 | 4.9% |
| ガラス・土石製品 | 3.0% |
| 紙・パルプ | 4.7% |
| 不動産業 | 5.1% |
| 運輸用機器 | 4.9% |
| 商社 | 7.3% |
| 電力・ガス業 | 6.5% |
| 建設業 | 9.3% |
| 飲料・たばこ | 8.6% |
| 繊維製品 | 4.9% |
| 化学工業 | -0.6% |
PBR:1倍以下
PBRとは、株価が1株当たり純資産の何倍になっているかを示す指標です。


株価が1株あたりの純資産の1倍の場合、株価と会社の資産価値は変わらないため、株価が適正価格と見なされます。


狙いどころとして1倍かそれより下なのは
株価が1株当たりの純資産よりも低いため、割安と判断されるからです。
| PBR | 評価 |
|---|---|
| 1倍 | 適正 |
| 1倍以上 | 割高 |
| 1倍未満 | 割安 |
もちろん、PBRはあくまでもひとつの目安であり、投資を行う際には、配当利回りや配当性向、継続増配、財務状況、経営方針なども考慮して投資判断を行うことが重要です。
高配当株のスクリーニングでPBRを1倍以下と設定することで、割安な高配当株に絞り込むことができます。これにより、配当金の継続的な支払いや、将来の成長可能性が高い企業を選定しやすくなります。
ただし、PBRが低い企業は、業績が悪化すると配当金が減ったり、なくなる可能性もあります。
また、PBRは業種や企業の状況によって大きく異なるため、単独で判断することは危険です。
以下に、高配当株のPBRの平均値を業種別にまとめます。
| 業種 | PBRの平均値 |
|---|---|
| 銀行 | 0.5倍以下 |
| 保険 | 0.5倍以下 |
| 不動産 | 0.7倍以下 |
| 製造業 | 0.8倍以下 |
| 小売業 | 1倍 |
| サービス業 | 1倍 |
高配当株のPBRの具体的な例
2023年10月の高配当株のPBRの具体的な例を以下に挙げます。
| 銘柄 | 配当利回り(%) | PBR |
|---|---|---|
| 第一三共 | 3.5% | 0.5倍 |
| LIXIL | 3.0% | 0.6倍 |
| アステラス製薬 | 2.8% | 0.7倍 |
| オリックス | 3.0% | 0.9倍 |
| 三菱UFJ銀行 | 4.0% | 0.6倍 |
これらの銘柄は、いずれもROEが7%以上であり、PBRが1倍以下であるため、割安で高配当が期待できる銘柄と言えます。
PER:15倍以下
PERとは、株価収益率の略で、株価が1株当たりの純利益の何倍まで買われているかを表す指標です。


PERが高いほど、株価が利益に対して割高であると判断されます。


PERが低いほど、株価が利益に対して割安であると判断されます。
なぜなら、1株当たり純利益が株価よりも大きいということは、現在の株価で株式を買い占めても、企業が1年間で稼げる利益の何倍もの金額を支払っていることになるからです。
| 株価 | 1株当たり純利益 | PER |
|---|---|---|
| 1,000円 | 100円 | 10倍 |
| 2,000円 | 100円 | 20倍 |
| 3,000円 | 100円 | 30倍 |
PERは、株価の割安感を判断する指標としてよく用いられます。PERが低い銘柄は、割安で買える可能性があるため、投資の対象として検討するとよいでしょう。
また、投資対象として選定する際にも色んな指標とあわせて比較する時にも使えます。
割安か割高か相場の判断の材料にも使われています。株価が1株当たりの純利益の何倍まで買われているかを表す指標です。
- 株価の割安感を判断する
- 投資対象の銘柄を選ぶ
- 売買のタイミングを判断する
またPERは、業種によって異なる傾向があります。
一般的に、成長性の高い業種のPERは高く、安定性の高い業種のPERは低くなります。
成長性の高い業種は、今後も利益が拡大していくことが期待されています。そのため、投資家は将来の利益成長を織り込んで株価を評価するため、PERが高くなる傾向にあるからです。
具体的には、以下の業種が成長性が高いと考えられ、PERが高くなる傾向にあります。
| 成長性が高くPERが高い業種 | PERが低い業種 |
|---|---|
| 医薬品 | 自動車 |
| 陸運業 | 商社 |
| 情報通信業 | 金融 |
| 小売業 | 保険 |
| サービス業 | 電気・ガス・水道業 |
- 情報通信業
- 医薬品業
- サービス業
一方、以下の業種が安定性が高いと考えられ、PERが低くなる傾向にあります。
- 食品業
- 電気・ガス・水道業
- 運輸業
同業種比較
PERは、同業種間で比較することで、より正確な判断を行うことができます。例えば、同じ製造業でも、自動車メーカーのPERは高く、食品メーカーのPERは低い傾向があります。
売上高営業利益率:7%以上
株価が1株当たりの純利益の何倍まで買われているかを表す指標です。


売上高営業利益率が高いほど、本業での収益力が高く、経営効率が良いと言えます。
売上高営業利益率は、以下の2つの要素によって決まります。
- 売上高:企業が得た売上金額
- 営業利益:売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を差し引いた利益


下記が売上高利益率の業種別の表です。※引用
| 業種 | 平均売上高営業利益率 |
|---|---|
| 建築業 | 4.02% |
| 製造業 | 2.69% |
| 情報通信業 | 4.75% |
| 運輸業・郵便業 | 0.24% |
| 卸売業 | 1.66% |
| 小売業 | 1.58% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 9.35% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 10.03% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 1.83% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 0.31% |
| サービス業(その他) | 3.82% |
業種によって売上高営業利益率は大きく異なる
理由は、業種によって原価率や競争環境が異なるためです。
例えば、情報通信業は、高額な設備投資や研究開発費が必要となるため、原価率が高くなります。
しかし、顧客から高い価格でサービスを提供できるため、売上高営業利益率が高くなります。
一方で、宿泊業・飲食サービス業は、人件費や食材費などの原価率が高く、競争も激しいため、売上高営業利益率が低くなります。
売上高営業利益率は、企業の収益性を判断する重要な指標
売上高営業利益率は、企業の収益性を判断する重要な指標です。売上高営業利益率が高いほど、本業での収益力が高く、経営効率が良いと言えます。
投資判断を行う際には、売上高営業利益率を参考にするとよいでしょう。売上高営業利益率が高い銘柄は、本業で高い収益力を維持している可能性が高いため、投資対象として検討するとよいでしょう。
売上高営業利益率は、あくまでも過去の業績に基づいた指標
売上高営業利益率は、あくまでも過去の業績に基づいた指標であり、将来の業績を保証するものではありません。
例えば、売上高営業利益率が高い銘柄でも、将来的に業績が悪化する可能性もあります。そのため、投資判断を行う際には、売上高営業利益率を他の指標と合わせて総合的に判断することが重要です。
自己資本比率:40%以上
自己資本比率とは、企業の総資本に占める自己資本の割合を示す指標です。


自己資本とは、企業が所有している資金であり、資本金や資本剰余金、利益剰余金などから構成されます。
総資本とは、自己資本と他人資本(負債)を合わせたものです。
自己資本比率が高いほど、他人資本に依存していないと言えます。
そのため、財務体質が良好であると考えられます。
自己資本比率は、企業の財務安全性を判断する重要な指標です。


- 自己資本:企業が所有している資金
- 総資本:自己資本と他人資本を合わせたもの
自己資本比率が高い企業は、以下のようなメリットがあります。
- 倒産リスクが低い
- 金融機関からの信用度が高い
- M&A(合併、買収)の際に有利
高配当株を選ぶ時に自己資本比率が60%以上が良い理由は、以下のとおりです。
倒産リスクが低い
高配当株は、配当金の支払いのために、企業の利益の多くを配当に回すため、財務体質が良好な企業を選ぶことが重要です。自己資本比率が60%以上であれば、他人資本の比率が低いため、倒産リスクが低いと判断できます。
配当金の継続性が高い
自己資本比率が高い企業は、財務体質が良好であるため、配当金の継続性が高いと考えられます。
株価の下落リスクが低い
自己資本比率が高い企業は、財務体質が良好であるため、株価の下落リスクが低いと考えられます。
ただし、自己資本比率が高すぎると、事業拡大や設備投資などの機会を逃してしまう可能性があります。そのため、自己資本比率は、業種や企業の状況によって適切かどうかを判断することが重要です。
具体的には、以下の業種は自己資本比率が高い傾向があります。
- 金融業
- 保険業
- 不動産業
これらの業種は、現金や有価証券などの資産を多く保有しているため、自己資本比率が高くなる傾向があります。
一方、以下の業種は自己資本比率が低い傾向があります。
- 製造業
- サービス業
これらの業種は、設備投資や研究開発費などの費用を多く負担しているため、自己資本比率が低くなる傾向があります。
自己資本比率は、企業の財務体質を判断する重要な指標ですが、業種や企業の状況によって適切かどうかを判断することが重要です。
流動比率:120%以上
流動比率は1年以内の支払い能力を分析する時に使わられる指標です。


比率が高いと企業の支払い能力が高く、安全で健全な運営をしている企業となります。
流動資産とは、1年以内に現金化できる資産のことです。
現金、預金、売掛金、在庫などが含まれます。
流動負債とは、1年以内に支払わなければならない負債のことです。
買掛金、借入金、未払金などが含まれます。



一般的に120%以上あれば問題がなく、200%あればかなり安全とされる



逆に100%を下回る企業はリスクが高い企業なので注意!
| 業種 | 流動性比率(2023年3月期) |
|---|---|
| 小売業 | 108.2% |
| 宿泊業 | 106.2% |
| 飲食サービス業 | 105.0% |
| 卸売業 | 110.7% |
| 建設業 | 131.5% |
| 製造業 | 132.6% |
| 情報通信業 | 217.0% |
| サービス業 | 208.8% |
連続増配している


安定した業績と経営基盤
連続増配を続けている企業は、安定した業績と経営基盤を有していると言えます。業績が安定していれば、配当金の継続的な支払いが期待できます。また、経営基盤がしっかりしていれば、配当金の減配や廃止のリスクが低くなります。
株主還元への積極姿勢
連続増配を続けている企業は、株主還元に積極的な姿勢を示しています。配当金は、株主への利益還元の重要な手段です。連続増配を続けている企業は、株主への利益還元に真摯に取り組んでいると言えます。
配当金の積立による資産形成
連続増配株の配当金を積立てることで、長期的に資産を形成することができます。配当金は、毎年一定額が支払われるため、積立てに適した投資対象と言えます。
もちろん、連続増配を続けている企業でも、業績悪化などにより配当金が減配や廃止になる可能性はあります。そのため、投資を行う際には、他の指標も合わせて考慮して投資判断を行うことが重要です。
連続増配株の期間が長い企業
※2023年10月時点
| 企業名 | 連続増配 | 配当利回り |
|---|---|---|
| 花王 | 33年 | 2.73% |
| SPK | 25年 | 2.74% |
| 三菱HCキャピタル | 24年 | 3.85% |
| 小林製薬 | 24年 | 1.54% |
| ユー・エス・エス | 23年 | 2.71% |
減配していない


高配当株を選ぶ時に減配していないということは
配当金の継続性が高い
減配の経験がある企業は、将来にわたって配当金を継続的に支払う能力が低い可能性があります。そのため、配当金の継続性を求めるのであれば、減配していない企業を選ぶことが重要です。
株価の下落リスクが低い
減配の経験がある企業は、株主から信頼を失っているため、株価の下落リスクが高くなる可能性があります。そのため、株価の下落リスクを抑えたいのであれば、減配していない企業を選ぶことが重要です。
投資家からの人気が高い
減配の経験がある企業は、投資家から敬遠される傾向があります。そのため、投資家からの人気を高めたいのであれば、減配していない企業を選ぶことが重要です。
ただし、減配していない企業でも、業績悪化や経営方針の変更などにより、将来的に減配する可能性はあります。そのため、減配していない企業を選ぶ際には、業績や経営方針を十分に分析することが重要です。
具体的には、以下の業種は減配の経験が少ない傾向があります。
- 食品
- 医薬品
- 電力
- ガス
- 不動産
一方、以下の業種は減配の経験が多い傾向があります。
- 製造業
- サービス業
これらの業種は、景気変動の影響を受けやすいため、減配のリスクが高いと考えられます。
なお、減配の経験があるからといって、必ずしも悪い投資対象になるとは限りません。減配の理由を十分に理解した上で、投資判断を行うことが重要です。
利益剰余金が毎年増え続けている
利益剰余金とは、企業がこれまでに得た利益を積み上げたものです。
税金や自己投資、配当や支出など差し引かれた数値で、積み立てた額を表しています。
つまり、利益剰余金が上がり続けているということは
企業が安定して利益を上げているということです。
そのため、財務体質が良好であると判断できます。
企業会計においては、貸借対照表の純資産の部に記載される、株主資本の一部です。
当期純利益とは、1期分の営業活動や投資活動、財務活動の結果として生じた利益のことです。
- 配当金の支払い
利益剰余金は、配当金の支払いの原資となります。利益剰余金が多いということは、配当金の支払い能力が高いということです。
- 内部留保
利益剰余金は、企業内部に留保することもできます。内部留保は、将来の事業拡大や設備投資などの資金として活用されます。
- 減資
利益剰余金を資本金に組み入れることで、減資を行うことができます。減資は、株主の資産を減少させる効果があります。
利益剰余金が毎年増え続けて得られるメリット
- 財務体質が良好である
利益剰余金は、企業がこれまでに得た利益を積み上げたものです。利益剰余金が増え続けているということは、企業が安定して利益を上げているということです。そのため、財務体質が良好であると判断できます。
- 配当金の継続性が高い
利益剰余金は、配当金の支払いの原資となります。利益剰余金が増え続けているということは、配当金の支払い能力が高いということです。そのため、配当金の継続性が高いと判断できます。
- 株価の下落リスクが低い
利益剰余金が増え続けているということは、企業の価値が向上しているということです。そのため、株価の下落リスクが低いと判断できます。
もちろん、利益剰余金が毎年増え続けていたからといって、必ずしも良い投資対象になるとは限りません。業績や経営方針を十分に分析した上で、投資判断を行うことが重要です。
- 安定した収益基盤を持つ
- 効率的な経営を行っている
- 財務体質が良好である
これらの特徴を持つ企業は、将来にわたって安定した成長が期待できるため、投資対象として魅力的と言えるでしょう。
EPSが高い(他社と比較)
EPSとは企業の稼ぐ力「収益力」と「成長性」がわかる指標です。
目安として、同業他社と比較する時に有効な指標で、他社と比較してEPSが高い方を優先すると良いです。
以下の計算方法で計算します。


- EPSが高い:企業の収益性が高い・成長率が高い
- EPSが低い:企業の収益性が低い・成長率が低い
高配当銘柄をスクリーニングするときに有効な理由は
EPSは企業の業績を直接的に示す指標であるから
EPSは、1株当たりの純利益を表す指標です。
企業の業績が好調であれば、EPSは高くなります。
したがって、EPSが高い銘柄は、企業の業績が好調で、安定した配当を継続できる可能性が高いと言えます。
EPSは配当性向との関係で考えることができるから
配当性向とは、当期純利益のうちどれだけを配当に回すかを表す指標です。
配当性向が高い銘柄は、配当金の総額が多いと言えます。
したがって、EPSが高い銘柄をスクリーニングすることで、配当性向が高い銘柄を効率的に見つけることができます。
EPSは株価に影響を与えるから
EPSは、株価を形成する1つの要因です。
EPSが高い銘柄は、株価が高くなる傾向があります。
したがって、EPSが高い銘柄をスクリーニングすることで、配当金に加えて、株価の上昇による利益も期待することができます。
配当利回りのみで判断しない
株式投資をする際、配当利回りだけで判断することはお勧めできません。
なぜなら、配当利回りが高いからといって、その銘柄が必ずしも良い投資先とは限らないからです。
理由として
配当利回りは企業の財務の健全性を考慮していない
配当利回りが高くても、財務が安定していなければ、長期的に配当を維持できない可能性がある。その結果、株価が下落し、将来の配当支払いが減少する可能性がある。
配当利回りは潜在的成長率を反映しない
企業が配当利回りを低く設定しているのは、成長を促進するために利益を事業に再投資しているためかもしれない。その結果、株価が上昇し、将来的に配当金が増加する可能性がある。
配当利回りは、株価に影響を与える他の要因を考慮していない
株価は、市場動向、経済情勢、企業ニュースなど様々な要因の影響を受けます。配当利回りだけでは、その銘柄の潜在的なパフォーマンスを完全に把握することはできない。
配当利回りは、株価に影響される
配当利回りは、1株当たりの配当金が株価の何%に相当するかを表す指標です。そのため、株価が下落すると、配当利回りは上昇します。
つまり、配当利回りが高くても、株価が下落している場合は、配当金の総額が減少している可能性があります。



高配当株は、配当利回りより安定性をみる事が大切!



スクリーニングをして堅実な銘柄を限定していこう!

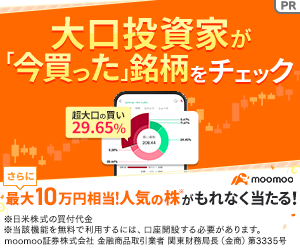










コメント